目次
高額療養費の支給
国民健康保険被保険者の方が病気やけがなどで医療機関にかかり、窓口で支払った医療費(保険適用分)の合計が自己負担限度額(下記参照)を超えたときは、交付申請により「高額療養費」として支給されます。
入院時の食事代や差額ベッド代などは保険適用外ですので、高額療養費の計算対象外です。ご注意ください。
「高額療養費」に該当する被保険者の世帯主の方へ健康課より申請のご案内をしています。
受診時の領収書が必要になりますので、捨てずに保管をお願いします。
※電話でキャッシュカードの暗証番号の聞き取りやATMの操作などをお願いすることは絶対にありません。そのような電話は詐欺ですので、怪しいと感じたら110番通報や警察署へご相談ください。
自己負担限度額
69歳以下の方
1ヶ月の自己負担限度額(入院時の食事代、差額ベッド代は除く)
| 所得要件 総所得金額等 *1 |
区分 *2 | 自己負担限度額 |
| 901万円超 | ア | 252,600円+(医療費10割-842,000円)×1% *4 〈140,100円〉*5 |
| 600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(医療費10割-558,000円)×1% *4 〈93,000円〉 *5 |
| 210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(医療費10割-267,000円)×1% *4 〈44,400円〉 *5 |
| 210万円以下 | エ | 57,600円〈44,400円〉 *5 |
| 住民税非課税世帯 *3 | オ | 35,400円〈24,600円〉 *5 |
*1:総所得金額等=総所得金額-基礎控除額
*2:限度額適用認定証における表記区分
*3:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の方
*4:「×1%」は、実際にかかった医療費の10割が「842,000円」「558,000円」「267,000円」を超えた場合、その超過額の1%を加算します。
*5:〈 〉内の数字は過去12か月のうち自己負担限度額に達した月が4回目以降になると適用される自己負担限度額です。
世帯の医療費を合算して自己負担限度額を超えたとき
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、それを合算して上記の自己負担限度額を超えた分が、「高額療養費」となります。
70歳から74歳までの方
1ヶ月の自己負担限度額(入院時の食事代等は除く)
| 所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 | |
| 外来の場合 (個人ごとに計算) |
世帯合算または入院の場合 | ||
| 課税所得金額 690万円以上 |
現役並所得者3 | 252,600円+(医療費10割-842,000円)×1% 〈140,100円〉 *4 |
|
| 課税所得金額 380万円以上 |
現役並所得者2 | 167,400円+(医療費10割-558,000円)×1% 〈93,000円〉 *4 |
|
| 課税所得金額 145万円以上 |
現役並所得者1 *1 | 80,100円+(医療費10割-26,700円)×1% 〈44,400円〉 *4 |
|
| 課税所得金額 145万円未満 |
一般 | 18,000円 [年間上限額144,000円] |
57,600円〈44,400円〉 *4 |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 *2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
低所得者1 *3 | 15,000円 | |
*1:現役並み所得者:課税所得が145万円以上の方、およびその方と同一世帯の方。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、健康課窓口への基準収入額適用申請により、一般の区分となります。
*2:世帯主及び同一世帯の国保被保険者の住民税が非課税の方
*3:住民税非課税の世帯で、世帯員の合計所得が必要経費や控除を差し引いた時に0円となる方。
*4:〈 〉内の数字は過去12か月のうち自己負担限度額に達した月が4回目以降になると適用される自己負担限度額です。
世帯の医療費を合算して自己負担限度額を超えたとき
「一般」、「低所得者1・2」の方は「外来(個人ごとに計算)」の自己負担限度額を適用したあと、「世帯合算または入院」の自己負担限度額を適用し「高額療養費」となります。
保険適用外の医療費の自己負担額やおむつ代、食事代、差額ベッド代などは含みません。
入院時の食事負担額ついては下記のページをご覧ください。
入院時の食事負担額について
限度額適用認定証等の交付について
国民健康保険被保険者の方が入院や高額な外来診療を受ける場合は、あらかじめ限度額適用認定証(区分が「オ」、「低所得者1・2」の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を健康課にて申請することをお勧めします。
交付された認定証を被保険者証または資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
注意:70歳以上75歳未満の方のうち、「一般」または「現役並所得者3」の区分に該当される方は、被保険者証と一体化された高齢受給者証を医療機関に提示することで限度額が反映されるため、認定証の手続きは必要ありません。
マイナ保険証(健康保険証をマイナンバーカードに紐付けした状態)で受診すると、医療機関でも自己負担限度額が分かるため、事前の申請が不要になります。
下記ページもあわせてご覧ください。
国民健康保険の各種医療証について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
申請に必要なもの
- 交付対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 交付対象者のマイナンバーカード
注意
- 国民健康保険税を滞納している世帯の方は、認定証の交付が受けられない場合があります。
- 世帯の国民健康保険被保険者の中に所得の申告をされていない方がいる場合は、該当にならない場合がありますので、申告をお願いいたします。
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療係
電話番号:0233-29-5792

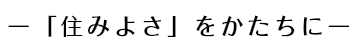
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。