介護サービスを利用するには
日常生活の中で負担や不安などを感じ、介護が必要となったときは、介護保険制度が皆さんの生活をサポートしてくれます。しかし、介護保険を利用するためには、どうすればよいかご存知でしょうか?
介護保険のサービスを利用するには、まず申請することが必要です。介護が必要と感じたら、まず申請しましょう。
申請できる人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスを利用できます。 - 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(注意:特定疾病)により介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
注意:特定疾病(厚生労働省により以下の16種類が指定されています)
1.がん(がん末期)、2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側索硬化症、4.後縦靭帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗しょう症、6.初老期における認知症(アルツハイマー病等)7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症、15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請から認定まで
1.申請
介護保険被保険者証を添えて市福祉事務所に申請します。
申請書は市福祉事務所高齢障害支援室にあります。
注意:第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は健康保険被保険者証が必要となります。
注意:申請は、本人又は家族が行いますが、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設で代行してもらうこともできます。
2.訪問調査・医師の意見書
介護保険担当職員が自宅を訪問し、心身の状況を調査します。
同時に、かかりつけの主治医に意見書を作成してもらいます。
3.認定審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で介護の必要性や程度について審査します。
4.認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当」、「要支援1から2」、「要介護1から5」の区分に分けて認定し、その結果を通知します。
「要介護状態区分」は要支援1から要介護5までの7段階に分かれています。
要介護状態区分によっては、利用できないサービスもあります。
「非該当」と認定された場合には、介護サービスは利用できませんが、なかでも生活機能が低下していると判断された方については、地域支援事業を利用できます。
6ヶ月ごとに更新の手続きが必要です
新規の方の認定の有効期間は、原則として6ヶ月です。
引き続きサービスを利用するためには、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新申請をし、認定を更新する必要があります。更新を申請すると改めて、調査、審査・認定が行われます。
サービス利用まで
1.ケアプラン作成の依頼・契約の締結
要支援1・2と認定された場合
地域包括支援センターに被保険者証を添えて申し込み、利用契約を結びます。
要介護1~5と判断された場合
指定居宅介護支援事業者に被保険者証を添えて申し込み、利用契約を結びます。
2.市福祉事務所への届出
「居宅サービス計画作成依頼届」を提出します。
3.ケアプランの作成・サービス利用開始
ケアプランに基づきサービスが提供されます。
利用者は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割(一定以上の所得のある方)を負担します。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810

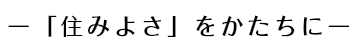
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。