折下吉延(おりしもよしのぶ)
1881年(明治14年)から1966年(昭和41年)
東京麻布の旧新庄藩主戸沢子爵邸で生まれる。
東京帝国大学卒業後、宮内省に入り、新宿御苑の園芸整備、奈良橿原神宮境内の拡張工事などに参画。35歳で明治神宮造営技師として明治神宮の森をつくりあげるなど、日本における公園整備の第一人者として、世界的に知られる。
関東大震災後、東京近辺の公園新設、街路樹の植栽を手がけ、昭和30年には日光東照宮の太郎杉伐採に際して保存を主張した。
新庄城址の中にある心字池は、昭和5年に氏の手によって完成された。
<新庄ふるさと歴史センター郷土人物館より>
折下吉延と最上公園
折下家は、代々新庄藩主戸沢氏の家臣だったということで、明治14年に東京都麻布の戸沢邸内で生まれました。
麻布中学、第一高等学校(現東京大学)に進学すると、洋画の三宅克己画伯の塾で水彩画を習い、風景画や静物画を描いたりと、この学生時代に絵画へ親しんだことが、後に造園設計に大いに役立つことになります。
その後、東京帝大農科大学農学科に入学し、近代の造園の発祥に貢献した原熙助教授から園芸学の講義を学び、造園の道を歩みはじめるきっかけとなります。
卒業後は、宮内省内苑寮園芸技師として勤務し、新宿御苑の管理や花壇の造成手入れに当たります。
明治天皇が崩御されたあと、政府は明治神宮造園を布告し、実行機関として「明治神宮造園局」が組織され、その技師主任に吉延が任命されます。
吉延は参道の取り付けや外苑の計画に主導的な役割を果たし、宮内省時代に自ら種をまき育てたイチョウもこの並木道に植えられ、今でも東京で最も美しい並木の一つとして人々に親しまれています。

明治神宮外苑の銀杏並木の風景
関東大震災のあと、焼け野原となった東京を復興するため、折下は臨時震災救護事務局事務官に任命され、復興事業の公園・緑化総括者として携わりました。
そして昭和2年、折下は公園づくりの手腕を買われ、郷里・新庄市の「最上公園心字池」の修景工事を監修し、同5年に完成させました。心字池は、幾度かの改修を経て、現在も最上公園でご覧いただけます。
最上公園の場所は下記の地図を参照ください
周辺案内図
地図はドラッグ操作でスクロールします。
このページに関する問い合わせ先
総合政策課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
電話番号:0233-22-2115
広報・地域づくり係
電話番号:0233-22-2116/0233-22-2117
システム統計係
電話番号:0233-22-2118

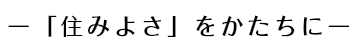
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。